この記事で解決できる疑問
このような疑問を解決できる記事をご用意しました。
消防士は巷で「寿命が短い」と言われていますが、実際のところどうなのか、元消防士の私が解説していきます。
おすすめの公務員予備校・通信講座
アガルート
初学者でも安心の充実カリキュラムと、元公務員の実力派講師陣による分かりやすい講義が魅力。通信講座でありながら予備校並みの手厚いサポートを受けられます。スマホでいつでもどこでも学習でき、忙しい社会人や大学生にも最適です。さらに合格者には受講料全額返金制度もあり、コスパも抜群。今なら期間限定の割引キャンペーン実施中!公務員試験合格への最短ルートを、アガルートで掴みませんか。
スタディング
業界最安級の受講料で、経済的負担を抑えて公務員試験対策ができます。スマホ完結型の学習システムで、通勤時間や昼休みなどスキマ時間を最大活用。AI問題復習機能が苦手分野を自動判定し、効率的に実力アップできます。フルサポートコースにすると模擬面接・ES添削が無制限。圧倒的なコスパで公務員合格を目指すなら、スタディングが最適です。
伊藤塾
法律系資格の名門として、圧倒的な合格実績を誇る伊藤塾。充実した答案添削や個別カウンセリングなど、手厚いサポート体制が魅力。特に法律系科目に強く、国家総合職や裁判所職員志望者から高い支持を得ています。本気で公務員合格を目指すなら、信頼と実績の伊藤塾で万全の対策を。
目次
消防士の平均寿命はどのくらい?
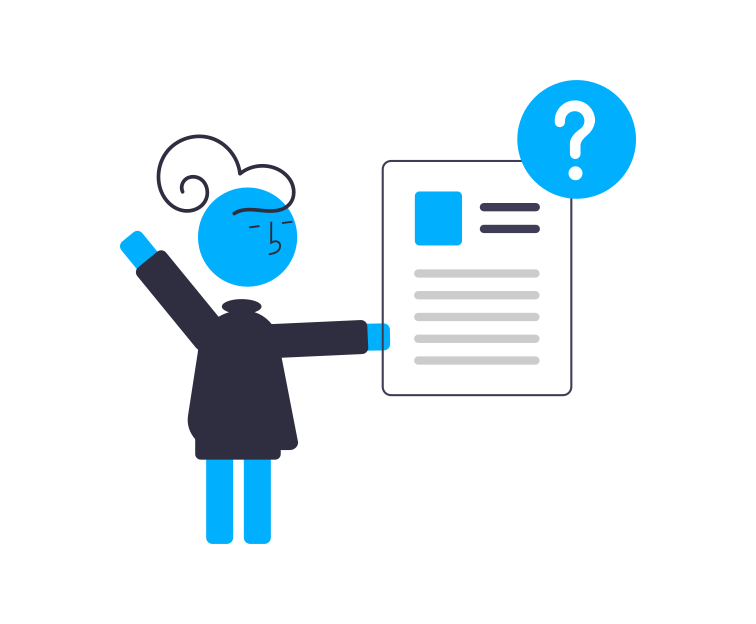
「消防士の平均寿命は65歳」という噂を最近よく耳にします。
結論、消防士の平均寿命が65歳という根拠はなく、消防士の平均寿命に関わる公的な統計は日本で取られていません。
消防士の定年が60歳から65歳に延長されているので、消防士の平均寿命が65歳なら、単純計算ですが65歳の定年前後で全消防士が亡くなる計算になってしまいます。
そのため、消防士の平均寿命が65歳だというのは、あくまで噂であるとお考えください。
しかし元消防士の私の感覚からすると、消防士の業務の特性や諸所の事情により、日本人の平均寿命(男性81.09歳、女性87.14歳)よりも消防士の平均寿命は短いのではないかとは思っています。
日本人の平均寿命の参照元:令和5年簡易生命表の概況
消防士の平均寿命が短いと言われる4つの理由
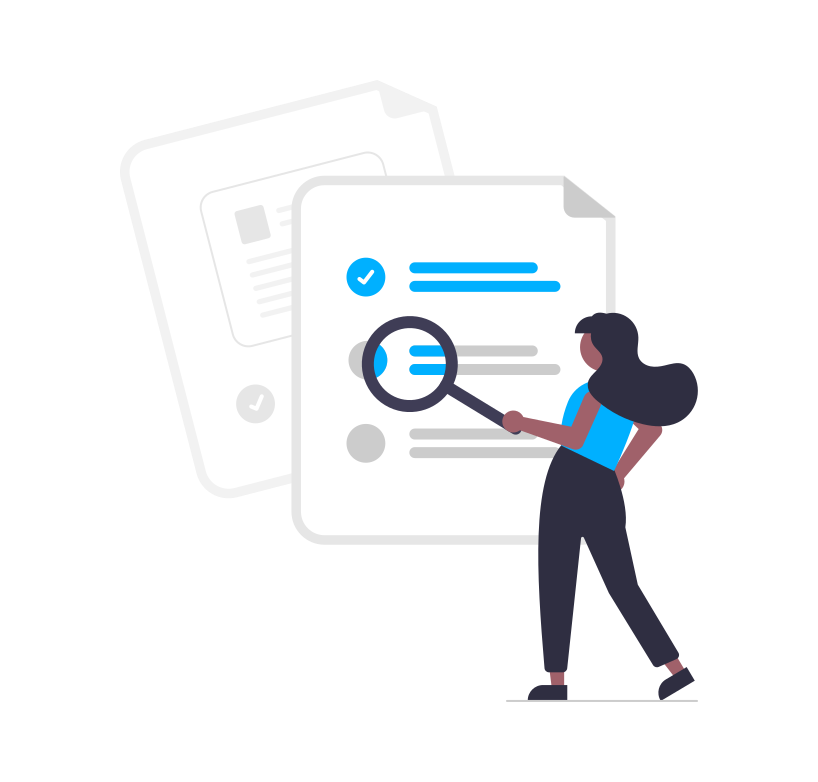
消防士の平均寿命が短いと言われる理由は、以下の4つが挙げられます。
消防士の平均寿命が短いと言われる理由
理由1:不規則な生活
1つ目の理由は、消防士の不規則な勤務形態にあります。
令和5年消防白書によると、全消防士のうち約8割の職員が交代制勤務(24時間勤務)に就いています。
24時間勤務は朝から翌朝まで働く勤務形態で、災害対応に当たる部隊です。
夜間帯は一応休憩時間とされていますが、災害が発生すれば災害対応にあたったり、業務が溜まっていれば寝る間を惜しんで仕事しなければならず、睡眠時間を十分に確保できない日がほとんどです。
以上のような交代制勤務の不規則な生活により、寿命が短くなる可能性があるでしょう。
消防士の勤務形態についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
-
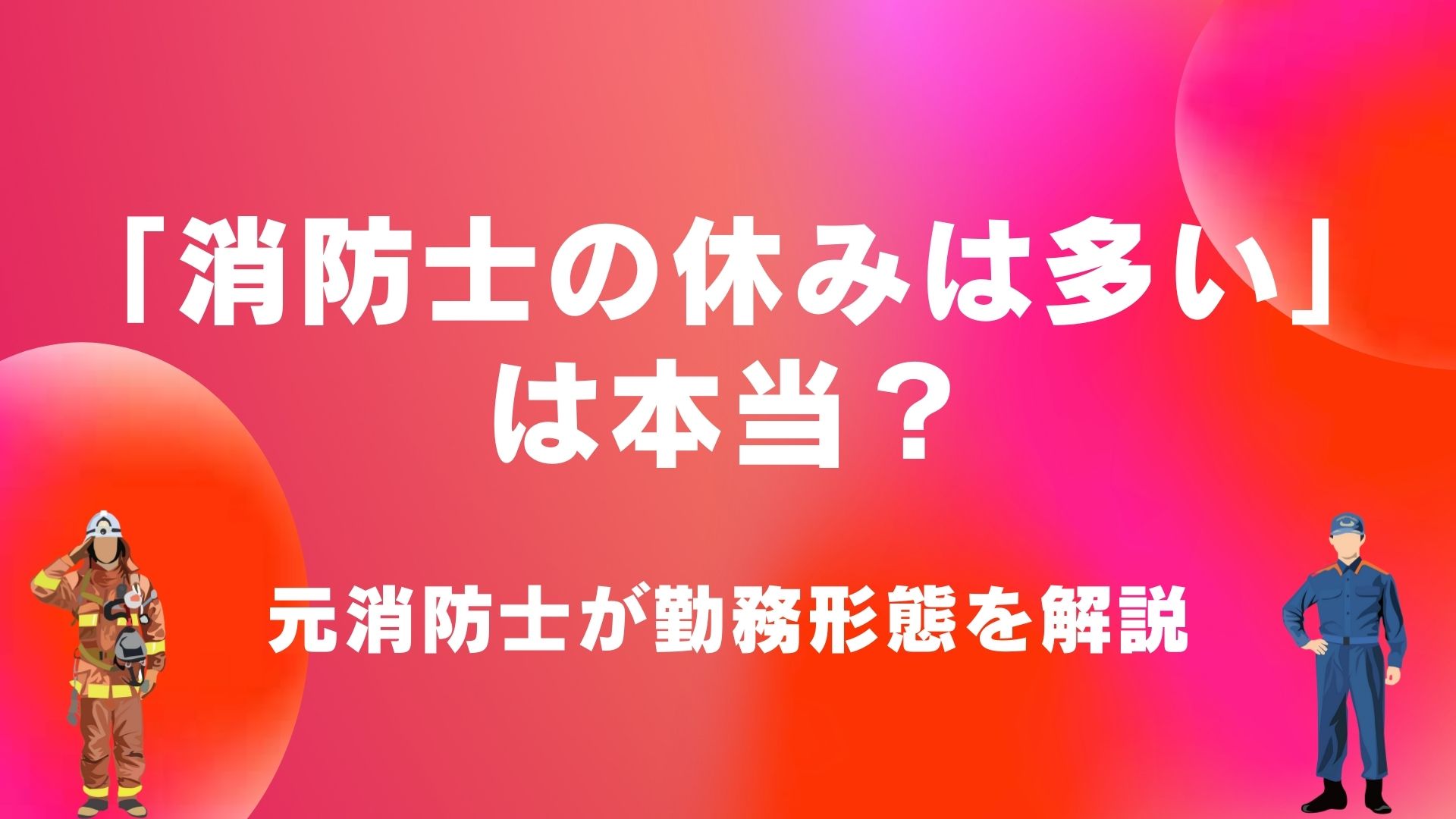
-
『消防士の休みは多い』は本当?元消防士が勤務形態について解説
この記事で解決できる疑問 1ヶ月の内3分の2が休みと言われる理由 勤務日の流れ 有効的な休みの使い方 このような悩みを解決できる記事を執筆しました。 消防士は、休みが多いというイメージを持っている人が ...
続きを見る
理由2:心身へのストレスが大きい
2つ目の理由として、心身へのストレスが挙げられます。
消防士の仕事は、心身にストレスのかかるタイミングが多いです。
救急隊は夜中も救急出動が多いので、一晩で2回も3回も起こされることがよくあります。

私は救急隊員のとき、夜中に救急出動で起きた際に立ちくらみや動悸を感じていました。特に救急隊は心身へのストレスが大きいよ!
このような心身へのストレスは、自分が気がつかないうちに体へのダメージとして蓄積されます。
理由3:不摂生が響く
3つ目の理由は、日常の不摂生がたたるからです。
交代制勤務の消防士は、勤務中は最低でも2食(昼と夜)用意しなければならず、自炊で用意するのは一人暮らしの職員とって負担が大きいです。
そのため、手軽なコンビニ弁当やカップ麺、出前で済ます職員がよくいますが、毎日そのような食事をしていると体に良くありません。
消防士は運動をするので太りにくいかもしれませんが、食事の不摂生は体に悪影響を及ぼします。
理由4:生活習慣が悪い
4つ目の理由として、生活習慣が悪い点が挙げられます。
消防士はいまだに喫煙者が多いです。
厚生労働省が実施した「令和4年国民健康・栄養調査」によると、令和4年の日本の喫煙率は男性24.8%、女性6.2%でしたが、私の肌感覚では男性消防士の喫煙率はいまだに40〜50%ぐらいはあります。
また消防士はお酒好きが多いので、飲み会での飲酒量もかなり多いです。
このようなタバコやお酒は、平均寿命に少なからず影響していると考えられます。
消防士の平均寿命を伸ばすための対策4つ
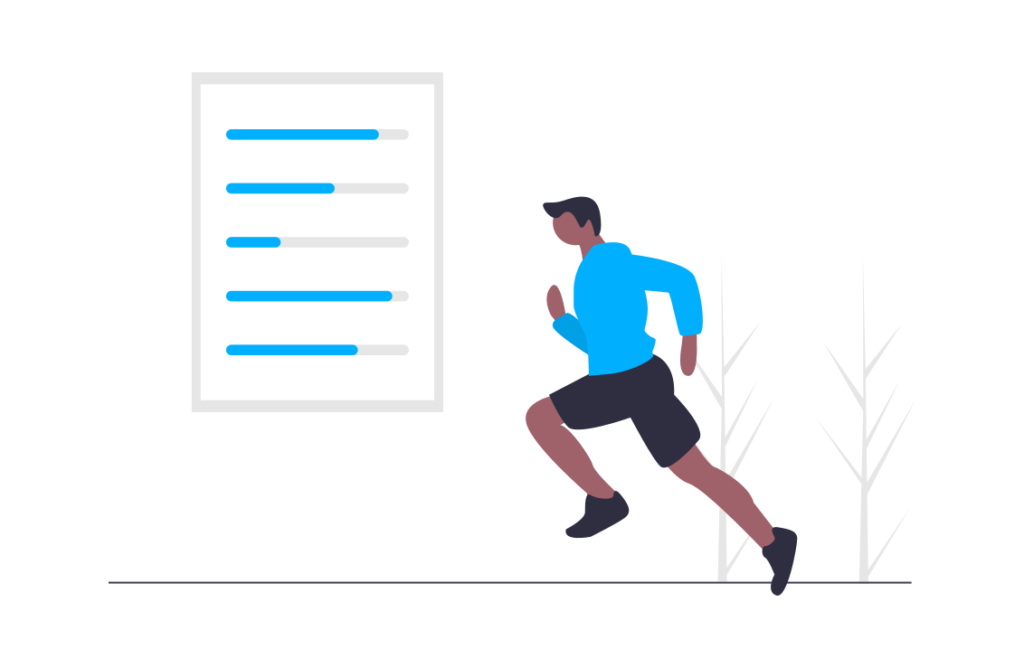
ここまで消防士の平均寿命が短い理由を解説してきました。
ここからは、個人でできる平均寿命を伸ばすための対策を紹介します。
平均寿命を伸ばす対策
対策1:規則正しい生活を送る
寿命を伸ばす上で最も重要なことは、規則正しい生活を送ることです。
しかし救急隊は出動が多く、なかなか規則正しい生活を送るのは難しいので、規則正しい生活を送りたいなら以下の方法を取りましょう。
毎日勤務は朝から夕方までの勤務なので規則正しい生活ができますし、交代制勤務でも消防隊なら救急隊より出動が少なく負担は少ないでしょう。
救急隊員として働く方の中には、給料がいいからという理由の方も多いと思います。
実際私は、消防隊より救急隊の方が給料がいいからという理由で救急隊で働いていましたし、救急隊の方が消防隊より毎月の給料が5万円よかったです。
しかし、給料面ばかり追いかけて体調を崩しては元も子もありません。
「規則正しい生活を過ごしたいけど給料面を理由に救急隊で働いている」という方は、給与収入以外での資産形成を考えてみてください。
対策2:なるべくストレス抱え込まない
寿命を伸ばすには、ストレスを抱え込まないことも大切です。
医師の和田秀樹さんは「長生きする人の特徴は、わがままであることだ」と言っています。
引用元記事:相手に合わせているとストレスで寿命が縮む…和田秀樹が教える「100歳まで生きられる人の最大の特徴」
今この記事を読まれている方にわがままになれとは言いませんが、自分なりにストレスを抱え込まない工夫が必要です。
消防士は心身ともにストレスがかかる仕事なので、以上のようなストレス発散法でストレスを抱え込まない対策をしてください。
対策3:食事を見直す
食生活の見直しも、寿命を伸ばす方法の一つです。
「食品の選択が寿命に与える影響の推定」という海外の論文によると、食事を最適化すると寿命が10年前後伸びるというデータが示されています。
毎日コンビニ弁当やカップ麺ばかり食べていると、食事が最適化されるわけがありません。
肉や魚、野菜に果物など、さまざまな食べものをバランスよく食べることが大切です。
対策4:生活習慣を見直す
寿命を伸ばしたいなら、生活習慣を見直しましょう。
上記で、消防士の喫煙率は高いとお伝えしましたが、喫煙やお酒の飲み過ぎ、運動習慣がない方は、生活習慣病になる可能性が上がります。
禁煙、適度な飲酒、適度な運動をして、病気に強い体を作りましょう。
労務管理に対しての消防全体での対策
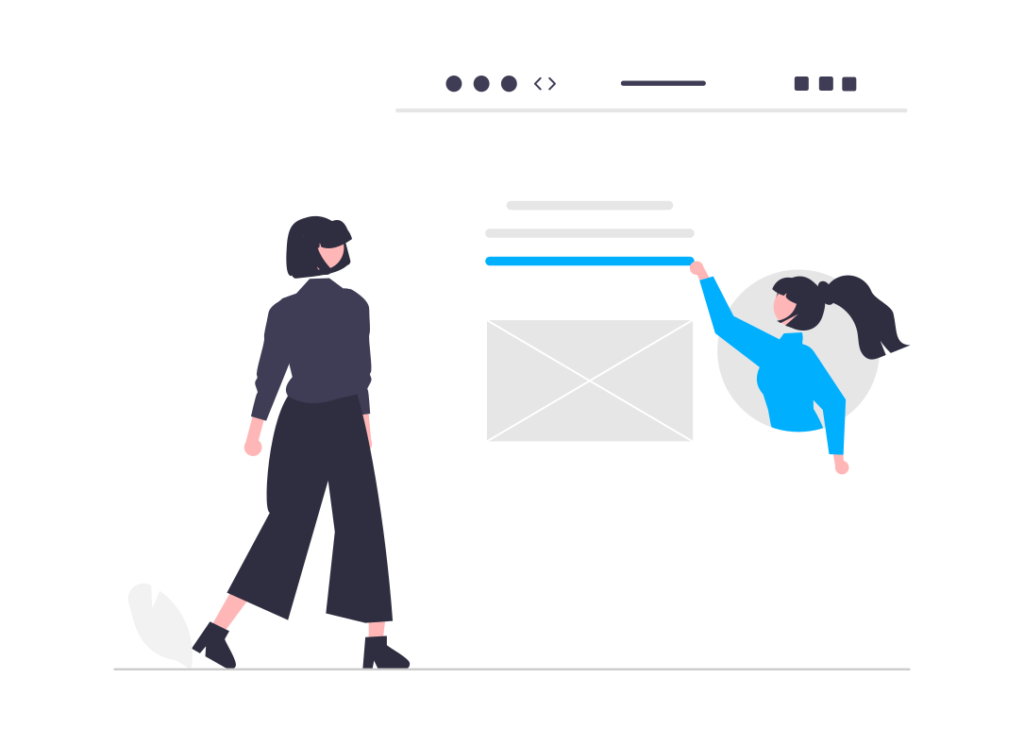
ここまで、個人でできる寿命延長対策をお伝えしてきました。
救急出動件数が年々増加している中で、消防全体としても救急隊の労務管理に対して、いくつかの対策を講じています。
消防としての対策1:隊員の増加
1つ目の労務管理は、隊員の増加です。
救急隊は通常3人で救急出動を行いますが、3人体制だと休憩時間の確保が困難なため、4人もしくは5人で勤務して休憩時間を確保する対策をとっています。
ただし隊員数を増やすという方法は、職員数が多い大規模な消防本部では可能ですが、小中規模の消防本部では職員数の観点から難しい可能性もあるでしょう。
消防としての対策2:出動隊の入れ替え
2つ目の労務管理として、出動隊の入れ替えを行なっている本部もあります。
出動隊の入れ替えとは、時間帯や出動件数に応じて、優先して出動する隊を入れ替える取組みです。
以上のように、優先して出動する隊を入れ替えることで、休憩を取りやすくなったり事務に充てる時間を確保できたりするメリットがあります。
消防としての対策3:コンビニの利用
3つ目の労務管理として、救急隊の食事や水分補給のために、コンビニ利用を許可している消防本部もあります。
広島市消防局では「A-pit(エーピット)」と称し、大手コンビニと連携して救急車でのコンビニ利用を開始しています。
この取組みにより、連続出動で食事や水分が取れない場合に栄養補給を行うことができ、救急隊員の負担軽減及び市民サービスの向上につながっています。
消防士は心身へのダメージが多い仕事
この記事のまとめ
- 「消防士の平均寿命は65歳」は根拠がない
- 消防士は大変な仕事だから寿命が短くなる可能性がある
- 寿命を伸ばすための対策を取ろう
消防士の平均寿命を調査した公的なデータはないので、消防士の寿命が65歳というのは噂に過ぎません。
しかし、消防士は心身ともにダメージが大きい仕事なので、寿命が短くなる可能性はあるでしょう。
特に救急隊は出動件数も多く、寿命を縮めて仕事をしていると言っても過言ではありません。
そのため、寿命を延ばすために、生活習慣を整えたり食生活を気にするなどの対策をとりましょう。
公務員を目指すなら、予備校・通信講座の利用がおすすめです。
実際に、私も公務員予備校を利用して消防士と警察官の試験に一発合格できました。
おすすめの公務員予備校・通信講座は以下の記事でまとめています。
-

-
公務員試験に合格するためのおすすめな予備校・通信講座を紹介
予備校名料金サポート体制合格実績二次試験対策アガルート23万円資格スクール大栄26万円スタディング10万円クレアール13万円伊藤塾30万円LEC35万円TAC34万円 ※料金は地方公務員上級相当のコー ...
続きを見る
『消防士の平均寿命』に関する質問などは、ご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です)
※いただいたコメントは全て拝見し、真剣に回答させていただきます。


